対談これからどうする経済学部!
対談者:東條正経済学部長 冨永佳与子瓊林会常務理事
会誌「瓊林」記事紹介(第114号より)
本日は、この度、経済学部長に3選され、今後2年間、経済学部の舵取りをされる東條学部長と昨年瓊林会の常務理事に就任され、女性会員による瓊林会活性化会議の座長としてもご活躍の富永常務に、ここ瓊林会館にお集まりいただき、「これからどうする経済学部!」というタイトルでお話し合いをしていただきます。
独立法人化後の法人評価で対応に追われる
(冨永)この度は、経済学部長3選を果たされまして、おめでとうございます。まず、学部長としてこれまで取り組んでこられたこと、これからの抱負等をお話いただけませんか。
(東條)
この2期4年間を振り返ってみますと、私が学部長になった最初の年が、創立100周年の年で、その年は100周年関係の行事の対応に追われたという感じでした。
2年目は、認証評価という、大学として基本レベルのものをちゃんと持っているかどうかということを外部から評価を受ける年で、それへの対応に追われました。
また、国立大学法人が国の組織でなくなって法人化した後、各国立法人ごとに6年ごとに中期の目標と計画を立てて、それが達成されたかをみる法人評価という制度ができ、昨年が実質的な評価の年でしたので、一昨年から昨年にかけてはこの対応に追われました。
この法人評価の結果次第で、今後国から交付される運営交付金等に差をつけられると言われておりましたし、またその結果が大学、学部ごとに公表されますので、大学を選ぶ受験生にも影響を与えると思われましたので、学部としても対応には必死にならざるを得ませんでした。
また、私共、大学の教員は今まで一方的に学生を評価するだけで、自分たちが評価されるのは初めての経験でしたので、その意味でも大変でした。最近その結果が内々に通知されましたが、学部、大学院共に良い評価を頂き、学長に予想以上に良い評価ではないかと言われたほどでした。
今年は、2期目の中期目標、中期計画というのを策定しなければならず、数年後にその結果を評価されます。しかし目標や計画をきっちりしてないと、良い評価を得られませんので、目標の設定が重要となります。直近の課題としてはそれが大きいもので、つまり、その中には、今後大学や学部をどうしていくかということを網羅しなければならないので、この目標設定は非常に大事なことだと考えています。
(冨永)
「良い評価を頂いた」ということですが、その評価のポイントはどういったところでしょうか。
(東條)
法人評価は、大きく教育、研究と分かれていまして、教育の場合は、経済学部の教育と経済学研究科(大学院)の教育で評価され、研究に関しては、経済学部、経済学研究科併せて評価を受けています。それぞれ掲げた目標を達成しているということで評価を頂いています。

(冨永)
「良い評価を頂いた」ということですが、その評価のポイントはどういったところでしょうか。
(東條)
法人評価は、大きく教育、研究と分かれていまして、教育の場合は、経済学部の教育と経済学研究科(大学院)の教育で評価され、研究に関しては、経済学部、経済学研究科併せて評価を受けています。それぞれ掲げた目標を達成しているということで評価を頂いています。

三学科を統一し総合経済学科に
(冨永)今の経済学部の学生さんは、どういった勉強をされているのか、お知りになりたい会員の方も多いと思います。お話し願えませんか。
(東條)
卒業生の多くの方がご存じのように、以前は、経済学科、経営学科、貿易学科の3学科制がだいぶ長く続きました。その後平成3年に貿易学科をファイナンス学科に改組しましたが、それは、バブル期にファイナンスに関心が高まったということがあります。その当時国立大学のファイナンス学科は滋賀大学と2校だけでした。
また、長崎大学には昭和26年に創設された働きながら学ぶ学生のための附属商科短期大学というものがありました。しかし、全国的にもだんだん夜間の短大への受験生の需要が減少してきたため、文部省によって各地の夜間の国立の短大を廃止して、近い学部に統合する方針が採られ、長崎大学でも商科短期大学部を廃止統合して平成9年に新しい形で経済学部が誕生することになり、学部定員も400名を越える大きな所帯になりました。
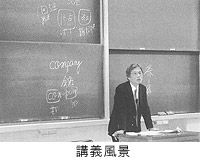 その際、今までの3学科を統一して総合経済学科とし、その中を6つのコースに分けるという形で、経営や会計、法律、情報等を中心にしたもの等に分けました。つまり、学部内での学生が選べるオプションを増やし、いろんな需要に対応できるようにという趣旨で国立大学の中では比較的に早めにコース制を採用しました。
その際、今までの3学科を統一して総合経済学科とし、その中を6つのコースに分けるという形で、経営や会計、法律、情報等を中心にしたもの等に分けました。つまり、学部内での学生が選べるオプションを増やし、いろんな需要に対応できるようにという趣旨で国立大学の中では比較的に早めにコース制を採用しました。ただし、このコース制を採用してから既に10年以上が経ちましたので、今後はコースの全面的な見直し等を含めて検討していかなければならないと考えています。
また、新経済学部に改組した時に、6つのコースのほかに夜間主コースといって商科短大の流れを継ぐコースも設置しました。それは働きながら勉強する学生に対応するために作ったものですが、このコースについてもそういった学生が極端に少なくなってきている中で、その全面的な見直しも大きな課題となってきています。
大学院は留学生と社会人が多い
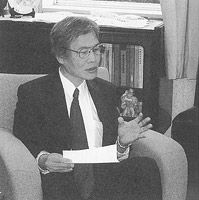 (冨永)
(冨永)私たちの時になかった大学院の方はいかがですか。
(東條)
現在、博士前期課程が2年、後期課程が3年となっています。定員は博士前期が15名、博士後期が3名です。理系は工学部などでは少なくとも大学院の修士課程を出なければ会社の就職が難しいところがありますが、文系の場合はそういう状況にはなっていませんので、小さい規模でやっていますが、うちの場合は留学生と社会人が多くなっています。
学部から大学院に進学してくる学生は、就職状態に反比例する傾向があり、昨年の前半までは景気がよかったので、学生が会社のほうに行ってしまって、大学院に進学する学生が少ない傾向もありました。
他大学でも文系の大学院は入学生を集めるのが難しい状況があり、学校によっては無試験に近い形で入学させているところもあるようですが、うちの場合は、専門試験も課して入学者を選抜しており、また終了時の修士論文や課題レポートの認定も他の大学院に比較しても体系的に厳しく行っていると思います。
どういったテーマで研究しているかというと、留学生の場合は中国出身の学生が多いので、中国関係のことをテーマにしている学生が多く、社会人は、自分の仕事の分野に関係したことをテーマにしている場合が多いといえます。
他大学でも文系の大学院は入学生を集めるのが難しい状況があり、学校によっては無試験に近い形で入学させているところもあるようですが、うちの場合は、専門試験も課して入学者を選抜しており、また終了時の修士論文や課題レポートの認定も他の大学院に比較しても体系的に厳しく行っていると思います。
どういったテーマで研究しているかというと、留学生の場合は中国出身の学生が多いので、中国関係のことをテーマにしている学生が多く、社会人は、自分の仕事の分野に関係したことをテーマにしている場合が多いといえます。
実践的エコノミストを育てることも必要
(冨永)大学には、理論系とかベーシックなものがもちろん必要だと思いますが、その先にどういう人材を輩出するかという考え方で、神戸大学のMBAのコースでは、大企業に於いて、引っ張っていく人材を育成するためのところであるといった考え方を採っており、グループ制で一つの課題を数人で研究するといった手法で注目されていますが、我が経済学部では、どのような社会人を育てていこうとされていますか。
(東條)
文部科学省は今、大学と大学院全体の中で、各々の大学の棲み分けを求めており、その時に6の分類を示して、どれとどれを目指すかはっきりするようにと求められています。
いわゆる高度の研究を中心にする大学と、職業人を育てる大学などといった分類がなされており、うちの場合ももちろん大学ですから、研究も重視しなければなりませんが、国際レベルの研究だけを目指す大学かというと、地方大学でそれだけでは難しいところがあります。職業人を育てる役割や、後は地域のために役立つような教育をもやっていかなければならないと思います。
ただ、今まで掲げてきた実践的エコノミストを育てるという目標も、具体的には何を目指すのかを改めて再検討していかなければならないと思います。
ただ、今まで掲げてきた実践的エコノミストを育てるという目標も、具体的には何を目指すのかを改めて再検討していかなければならないと思います。
中国との関係を重視した学術交流等を
進めてはどうか
(冨永)かつての高商時代のプライドを持ち、やってこられた先輩方を初めとして、瓊林会の会員の皆様には、現在の経済学部がもっと憧れのある学部であって欲しい、自分たちの母校が常に憧れられる存在であって欲しいという想いがありますが、残念ながらだんだんそういうものが失われているのではないかという危機感も感じています。今の大学に「ああ、あの大学ね!」という何かが欲しい。例えば「最先端の研究をやってほしい」とか、「国際交流をやってほしい」とかいろんなご要望をお伺いしました。その中のポイントとして、先ほど中国の留学生が多いというお話がありましたが、長崎には、中国の総領事館が長崎のためにだけ置いてあるそうです。それは長崎と中国の深いつながりがあるということでしょうし、経済学部では、そのことがまだ、うまく活かされてないのではないでしょうか。姪が東中学に行っていますが、県の方針で修学旅行は上海に行くそうです。そういったベースもあるので、中国との関係を重視して、多くの学生を受け入れるとか、研究者を交換するとか中国の大学と単位交換をするとかアクティブなやり方、先ほどカリキュラムの話もありましたが、そういった特徴的な講座の組み方もあっていいのではないかと思います。経済学部がそういった形で動き出してくれば、瓊林会としても財政的支援や全国のネットワーク組織の活用も図れるのではないかと思います。
(東條)
経済学部では、戦後早くから東南アジア研究所が設置され、瓊林会からも多大な支援を受けてきました。もともと長崎というところは、中国との交流の面で中核の都市であったわけで、高商時代においては、全国的に見ても朝鮮とか満州の研究が進んでいました。戦後もその伝統を生かすために、アジアの中でも中国や朝鮮の研究をメインにした研究所を目指したようですが、当時は同地域の多くが社会主義国家であったため政治的にまずいということで、東南アジア研究所という名称になったようです。
その後、アジア研究の伝統はあるのに充分な研究の成果が出ていないのではないかという御批判が強くあります。確かに研究成果の産出量が充分でないという状況があると思いますが、それはアジア地域を中心的な研究テーマにしている教員が少ないという要素もあると考えます。
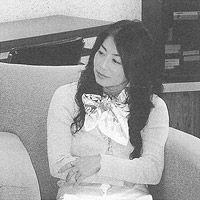 もちろん、経済学や経営学というのは普遍的なもので、特定の地域にこだわる必要はないのですが、そういう研究所を活かすためには、やはり専門にその地域を研究する教員が多くいたほうがいいので、今後はアジアを研究テーマにしている研究者を増やしていきたいと考えています。
もちろん、経済学や経営学というのは普遍的なもので、特定の地域にこだわる必要はないのですが、そういう研究所を活かすためには、やはり専門にその地域を研究する教員が多くいたほうがいいので、今後はアジアを研究テーマにしている研究者を増やしていきたいと考えています。(冨永)
九州大学とタイアップして中国との経済学交流を推進している方は、わが経済学部のOBですし、大阪支部にも中国工場の社長を務めてリタイアされた方もいらっしゃいます。そのようなOBで実学を知っている方を、大学に迎えて頂くと、現地の状況もよく分かるし、人脈もあるので、向こうの先生につながることも簡単ではないかと思います。瓊林会は学部のためなら色んな労をとると思いますので、OBの活用についてご検討いただくのも一案ではないでしょうか。
それから学生について、少子化で数が少なくなっていると思いますが、若年層だけを対象にするのではなくて、年配の方でもいいのではないかと思います。アメリカでは、外に出て働いて学費がたまったら大学に戻って、勉強してまたステップアップしてというのがあります。大学は全部入れてあげて卒業を厳しくするという方法をとると、意欲のある方はそこで学んでステップアップして他の仕事にもつくことができるチャンスが与えられると思いますが。
(東條)
今後、少子化が急速に進行する中で、社会人や退職した団塊の世代をターゲットとして考えない手はないと私も考えています。ただ難しいのは、昔と違って国立大学の授業料が高い。1年間に50数万円かかり、社会人や年金生活者には相当に無理があります。もっと柔軟に対応できないのかと文科省等に話はしているのですが…。
地域経済を活性化するための
「行政経営学」の講座はできないか
(冨永)昨日、長崎支部の女子会員で構成している「瓊林会活性化対策会議」を開催したのですが、その一人で長崎市の職員の方からこういうお話がありました。彼女は企業誘致を担当されていて、「これだけのお金を使って企業を誘致して、どれだけの利益が地域にもたらされるのかというのをはじき出して、その資料を議会に諮らなければならない場合に、自分は大学で何を学んできたのかと痛感します。」即ち、地域といえども稼がなければならないので、マネジメントとか経済的な考え方が行政に必要だというのを初めて体感したということでした。社会に出て、「あ、こんなことを学んでいればよかった」ということがあります。学校側としても卒業生の課題に応えられるようなカリキュラムの編成があってもいいのではないでしょうか。特に地方行政の場合、経営の感覚がなければ、地域が沈んでしまいます。長崎は、大きな企業も少なく、産業界だけで何かを変えていくのは難しい。長崎のような街こそ、産・官・学一体となって地域を支えていかねばなりません。長崎県や長崎市と「行政経営学」といった講座を立ち上げてもよいのではないでしょうか。他にない、先進的な取り組みとなり、長崎経済の大きな特徴となります。体系的に教えるところがないというのは日本の将来に向けても懸念されるところです。
(東條)
大学側に、そういった体制が必ずしも整っていない部分があるかも知れません。大学院で社会人に門戸は開いていますが、行政を含めた多様なニーズに対応するところまでいっていない部分もあると思います。また、先ほど、いっそのこと入学希望者は無条件に全部入学させてはという話もありましたが、現在定員を90%切るか、110%を超えて入学させるとペナルティが来るというシステムになっています。それは何故だというと、私立大学の経営が苦しいので、定員を超えて入学させることはしないようにというのが文科省の要請です。独立の法人になったのですからもっと各大学の自由を認めてもらってもいいのではないかと私個人は思っていますが。
大学側に、そういった体制が必ずしも整っていない部分があるかも知れません。大学院で社会人に門戸は開いていますが、行政を含めた多様なニーズに対応するところまでいっていない部分もあると思います。また、先ほど、いっそのこと入学希望者は無条件に全部入学させてはという話もありましたが、現在定員を90%切るか、110%を超えて入学させるとペナルティが来るというシステムになっています。それは何故だというと、私立大学の経営が苦しいので、定員を超えて入学させることはしないようにというのが文科省の要請です。独立の法人になったのですからもっと各大学の自由を認めてもらってもいいのではないかと私個人は思っていますが。
職業教育の一環として
瓊林OBにも協力してほしい
(冨永)彼女たちの意見の中に、就職する前に職場を見ておきたかったというのがあります。卒業生が働いている現場を在学中に見ていたら、職業選択も違っていたかもしれないとのことですが。
(東條)
今、インターンシップ制度というものがあって、3年生になると希望者は会社での一定期間の実地体験をしていますけれども、もっと職業教育といったものが必要だと思います。確かに昔以上に社会のことを知らない学生が多すぎます。先ほどの公務員の話にしても、地域を活性化していくためにはいろんな知識が必要で、重要な役割を持っているということをもっと知らしめる必要があると思います。
いま、大学卒業生の相当数が就職しても3年以内に辞めてしまうという深刻な話もあり、やはり低年次からそういった教育が欠かせないと思っています。私が、いま、入学してきた新入生にまず言っているのは、4年間の学生時代をエンジョイしたいと思っているかもしれないが、2年半後には就職を考えなければならなくなり、その時までに「私を採ったら他の学生とは違いますよ」と差別化ができないと、希望する就職先に採用されるのは難しいので、大学の4年間といってもそんなに時間はないんだよという話をしています。
そうはいっても、学生には実感として分からないと思いますので、もっと低年次生からカリキュラムの中で職業教育を考えなくてはならないと思っています。その場合に、たとえば、瓊林会のOBの人達に講義に出向いてもらって、社会とはこういうところだと話をしてもらうことも一つの方法だと思います。
(冨永)
瓊林会のネットワークを活用していただくのは、瓊林会としても意義ある取り組みとなると思います。
(東條)
私立大学の強みは、卒業生と大学との一体感だと思います。我々も国立大学法人という私立に近い形式になったので、その私立の強みを取り入れないといけないと思います。もともと旧高商系というのは、国立大の中でも同窓会との一体感が強いので、お互いの独立性を保ちながら、協力関係を深めていくことが大事だと思います。その中の一環として、先ほどのキャリア教育に参加していただくことも検討の対象となると思います。
(冨永)
瓊林会のネットワークを活用していただくのは、瓊林会としても意義ある取り組みとなると思います。
(東條)
私立大学の強みは、卒業生と大学との一体感だと思います。我々も国立大学法人という私立に近い形式になったので、その私立の強みを取り入れないといけないと思います。もともと旧高商系というのは、国立大の中でも同窓会との一体感が強いので、お互いの独立性を保ちながら、協力関係を深めていくことが大事だと思います。その中の一環として、先ほどのキャリア教育に参加していただくことも検討の対象となると思います。
経済学部としての意識の希薄化
(冨永)最近の学生は経済学部という意識が希薄になっているのではないでしょうか。以前「瓊翠会」という経済学部女子学生の会があって、主体は女子学生で卒業生と一緒にやっていたのですが、そのような活動を通じて、経済学部を感じていただけたようです。その意味で、今の学生さん達に、アルバイトでもいいから瓊林会の仕事を、例えばホームページをつくることなど手伝っていただいては如何でしょうか。私達も当時瓊林会のいろんな行事のお手伝いをさせていただき、それが良い思い出になっています。
(東條)
当時の学生と今と違うのは、経済学部生という意識がどんどん希薄化していることだと思います。それは、経済学部生という意識より長大生という意識が強くなっており、サークル活動でも、経済系のサークルより本学のサークルに入る傾向が強くなっています。長崎大学に入ったのだから、長大の本学のサークルに入るのが当たり前という感覚のようです。それが強くなってくると、経済学部OBとのつながりも薄れてくることになります。
最近、長崎大学全学同窓会というものができましたが、年配の方々には、急に学部を越えて同窓会活動を一緒にやれといわれても、受け入れにくい部分もあると思われます。
しかし、逆に最近の学生、卒業生は長大生という意識が強まっていると思われますので、経済学部生という意識が希薄化するのにどう対処するのが、経済学部や同窓会にとっては今後大きな課題になってくると思います。
しかし、逆に最近の学生、卒業生は長大生という意識が強まっていると思われますので、経済学部生という意識が希薄化するのにどう対処するのが、経済学部や同窓会にとっては今後大きな課題になってくると思います。
「アジア」と「地域」がキーワード
(冨永)本日のメインテーマとなっております、「経済学部をこれからどうする!」ということについて学部長のお考えをお聞かせ願えませんか。
(東條)
やはり「アジア」と「地域」というのがキーワードになると思います。アジアといった場合はこれまでの交流の歴史からいっても、中国、韓国や東南アジア諸国などが中心になるでしょうし、他の学部と連携をとって、全学的な立場でアジア研究の推進役になることもこれからの課題だと思います。また地域の場合、地域に深く関わっている県、市とタッグを組んで地域の活性化に取り組みといったことも必要だと思います。
ただ、大学の問題点として、一般的に大学人は研究を主眼にする考え方が強く、人材育成だとか、地域の活性化だとか、産業の育成だとか社会に関わる視点が希薄な部分もあると思われますので、大学人の意識改革にも取り組まなければならないと思います。
(冨永)
全学的な取り組みでは、経済学部にコーディネーター的な役割も求められますね。
最後に、学部長の教育の理念といったことで日頃お考えになっていることをお話下さい。
 (東條)
(東條)大学に最も求められるのは、考える力を養うことで、将来どんな職業についても最も重要なのは自分の頭で考える力だと思います。私は学生に次のようなことをよく話しをします。高校までは覚えることが大事だけど、大学に入ったら教わったことをそのまま鵜呑みにするなと。例えば高校までは1+1=2でよかったけれども、大学では1+1=2以外に答えはないのかなと考えなさいと。というのは2進法の世界では1+1=10となるのだから、それが大事ですよということです。学問的な知識を習得させると同時に、論理的な思考力を鍛え上げ、独創性、オリジナリティを養うという点が最も重要な大学の役目だと考えています。
(冨永)
これからの経済学部の未来が拓けてきたような気が致します。瓊林会の会員の皆様も、「共に行こう!」と言って下さると思います。本日は、本当に有難うございました。